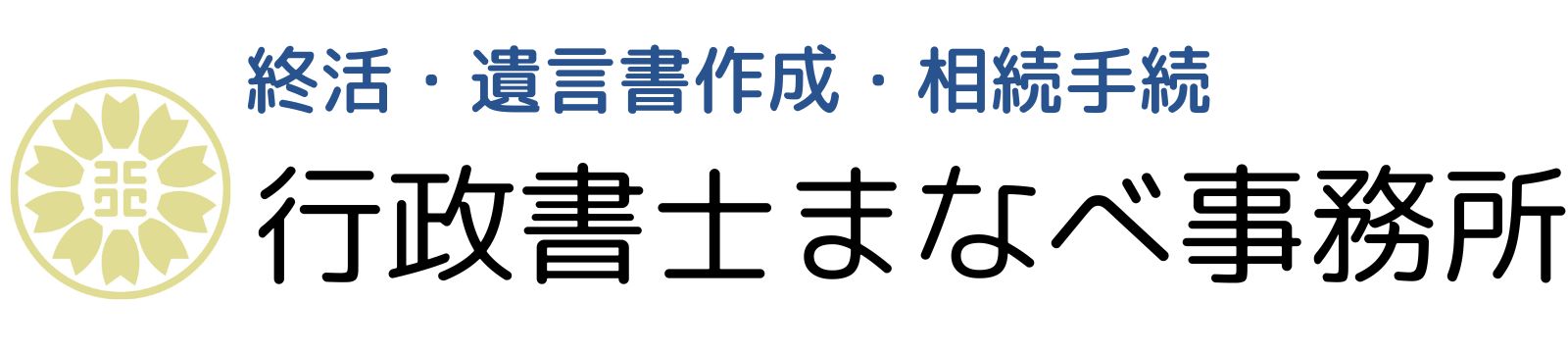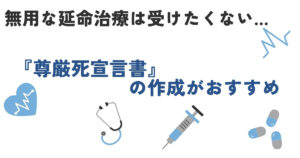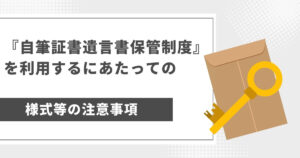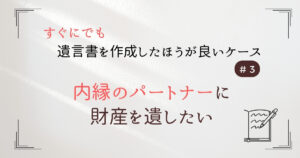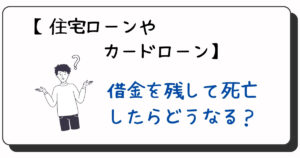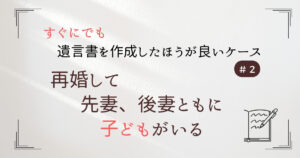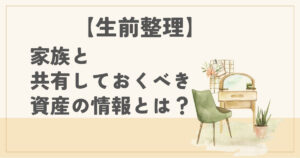最低限の相続分を守る「遺留分」とは
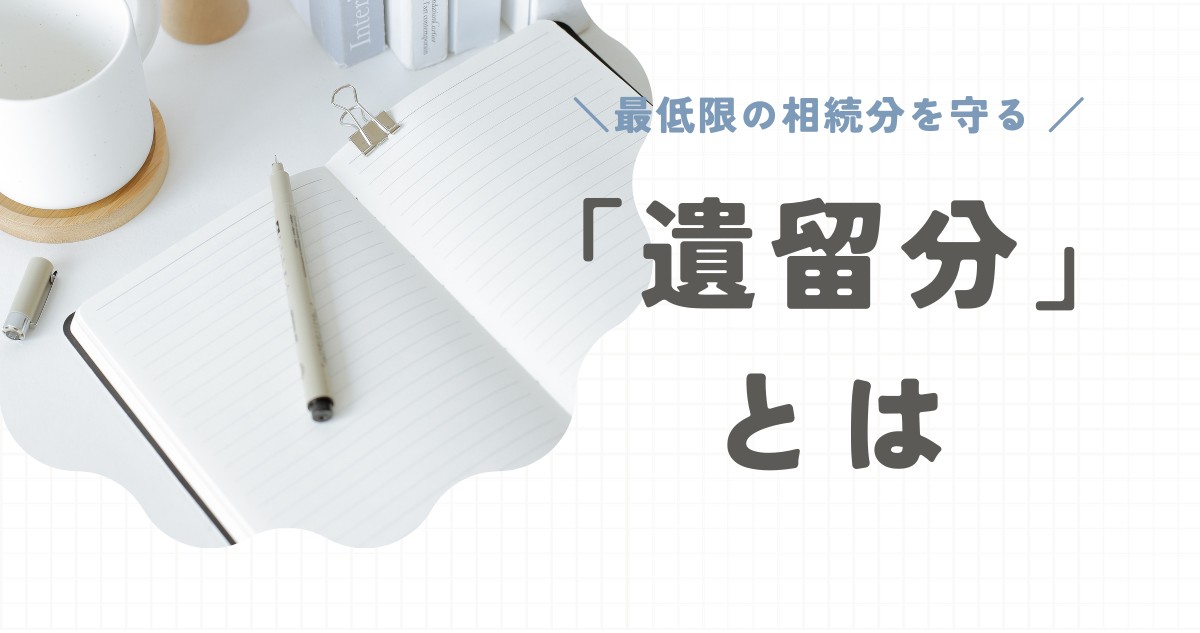
自由に遺言書を作成できるといっても、「家族以外の誰かに全財産を相続させる」という遺言を残されたのでは残された家族(法定相続人)はたまったものではありません。
このように、法定相続人以外の第三者に財産を譲ったり、法定相続人の相続割合を変更し、極端に少ない財産しか相続させないなど、通常とは異なる相続をさせようとした場合でも、法定相続人には最低限の相続することができる権利が認められています。
これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。
「『法定相続分』は必ずもらえるんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実は、法定相続分とは遺産を分ける際の目安にすぎないため、必ずもらえるという保証があるわけではないのです。
遺留分は、残された家族の生活を保障するために、遺言書でも手を出せない最低限の金額は必ず相続できる権利ということができます。
遺留分に関するポイントは3つ
1. 遺留分は「権利」であるということ
1つ目は、遺留分は権利であるということです。
つまり、もし実の息子である自分には1円も相続させないという内容の遺言書があったとしても、それで納得するのなら遺言書の通り1円も相続しないとしても何も問題はありません。
しかし、「それでは納得がいかない、自分には遺留分という権利があるのだから相続させろ!」というのなら最低限保障されている金額を相続することができるのです。
遺留分はあくまでも「権利」なので、行使するかどうかは相続人次第ということです。
2. 兄弟姉妹には遺留分は「ない」
2つ目は、遺留分が認められるのは、配偶者、子や孫(代襲相続人を含む)などの直系卑属、および直系尊属(親や祖父母)に限られるということです。
つまり、法定相続人であっても、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。
兄弟姉妹は亡くなった方(被相続人)とは別生計であることが一般的なので、遺産を相続できなくても生活上困ることはないだろう、という考えに基づいています。
そのため、例えば子供のいない夫婦の一方が死亡した場合に、もう一方に全額相続させるという内容の遺言書があれば、全額相続することができ、亡くなった方の兄弟姉妹から「私たちも相続人なんだから少し遺産を分けてくれ」と言われたとしても、法的にはまったく効力はありません。
3. 遺留分はいくら保障されるか
ポイントの最後は、遺留分の保障額についてです。
遺留分の割合は、基本は被相続人の財産の2分の1であり、親などの直系尊属のみが相続人の場合は財産の3分の1となります。
遺留分は以下の手順で計算します。
①相続財産全体額から遺留分額を算出する。
(遺留分の割合が2分の1の場合は、「財産×2分の1」)
②相続人の法定相続分にしたがい分ける
<被相続人の3,000万円の財産の遺留分を求める場合>
(法定相続人は配偶者と子3人)
配偶者:3,000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=750万円
子ども(1人あたり):3,000万円×1/2(遺留分)×1/6(法定相続分)=250万円
遺留分の合計は財産の2分の1となるので、1,500万円(750万円+250万円×3)となります。
遺留分の割合をまとめると以下のようになります。
(子や父母が複数いる場合はさらにその人数で割ります)
| 法定相続人 | 配偶者だけ | 子だけ | 配偶者と子 | 父母だけ | 配偶者と父母 |
| 配偶者 | 1/2 | ー | 1/4 | ー | 1/3 |
| 子 | ー | 1/2 | 1/4 | ー | ー |
| 父母 | ー | ー | ー | 1/3 | 1/6 |
| 遺留分の合計 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
なお、遺留分は金銭債権となるので、遺留分を請求する者に対する支払いは現金に限られます。
遺留分はいつまで請求できる?
遺留分を侵害された場合、財産を多く相続した受遺者や受贈者(遺留分を侵害した相手)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
この遺留分侵害額請求は、相続開始(被相続人の死亡の日)および遺留分の侵害を知った日から1年以内、かつ相続開始から10年以内に行わなければならず、この期限を過ぎると遺留分の権利が認められなくなるので注意が必要です。
さいごに
遺留分制度を理解することは、相続を考えるうえでとても大切なことです。
さらに、遺留分は遺言書を書く時にも考慮すべき事項です。
遺言書をしっかりと作成したとしても、相続人(兄弟姉妹以外)の遺留分を侵害(遺留分より少ない額しか相続させない)するような遺言書を残すことは争いのもとになることもありますので十分に注意が必要です。