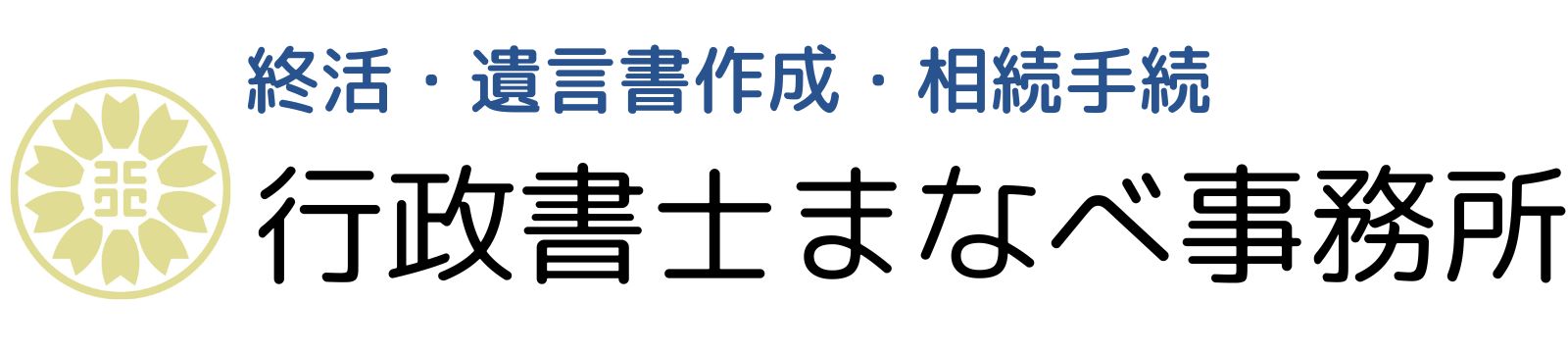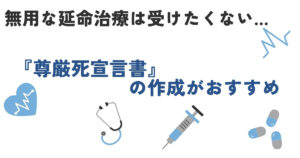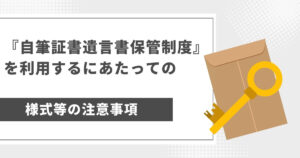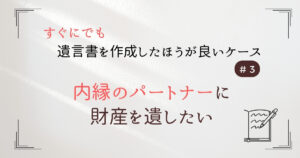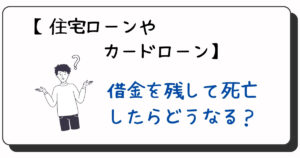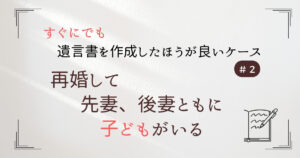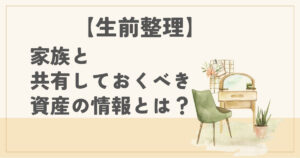【遺言書の種類】自筆証書遺言と公正証書遺言どっちがいいの?
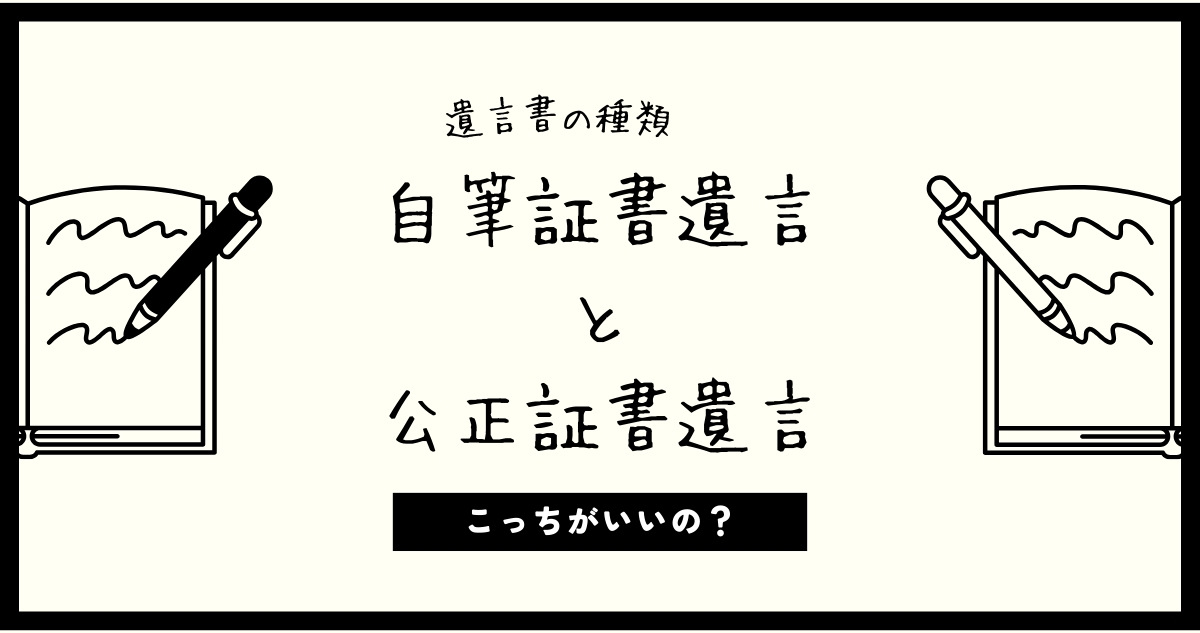
遺言書にはいくつか種類があり、一般的によく使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言のふたつです。
ここでは、それぞれの遺言書はどういうものなのか、またメリット・デメリットを含めて解説します。
自筆証書遺言
遺言の内容をすべて自分で記載(自筆)し、日付を書き、署名・押印して作成する遺言が自筆証書遺言です。
専門家に頼まずとも、紙とペンがあれば作成できるため、費用をそれほどかけずに手軽に作成することができます。
ただし、専門家のチェックを受けない場合は、様式に不備があったときは遺言書として認められない可能性もあるので注意が必要です。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合、死後に遺言を執行する場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きをとる必要があります。
(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認は不要です。)
検認とは、家庭裁判所において、遺言書の内容を確認する作業のことをいいます。
相続人立会いのもと、遺言書を開封し、日付や筆跡、署名の状態などを確認し、確かに遺言はあったということを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きを行います。
※検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
そして、検認の手続きが終わるまでは相続手続きをすることができません。
法改正で利便性が向上
自筆証書遺言については、近年、法改正によって利便性が向上しています。
法務局で保管すれば検認が不要に
遺言書を作ったはいいものの、紛失してしまったり、盗難にあう、第三者に改ざんされてしまうといってリスクがありました。
そこで、2020年7月から作成した自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が開始されました。
この制度を利用すると遺言書を執行する際に検認が不要となり、スムーズに相続手続きを進めることがでます。
財産目録をパソコンで作成可能に
2019年の法改正で、財産目録の部分はパソコンで入力して作成することも可能となりました。
いままでは、財産目録の部分も含めてすべて手書きしなければいけなかったので、財産の種類が多い場合などの手間が少なくなりました。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット・デメリットとしては以下のようなものがあります。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからず手軽に作成できる
- 内容を他人に知られることがない
自筆証書遺言のデメリット
- 書く手間がかかる
- 様式に不備があり無効になる可能性がある
- 紛失や盗難、改ざんのおそれがある
- 自分の死後、遺言書が発見されない可能性がある
- 遺言の執行時に検認手続きが必要(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は検認は不要)
公正証書遺言
証人の立会いのもとに、公証役場において公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。
相続財産や相続人の関係が複雑なときは、専門家を利用する公正証書遺言がおすすめです。
実印や戸籍謄本などの必要書類を用意し、公証人と打ち合わせを行い、2人の証人の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。
遺言書の原本は公証役場に保管し、正本と謄本の2通は遺言者の側で保管します。
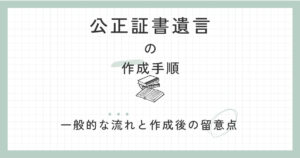
費用と手間はかかりますが、無効な遺言書となることはなく、されに盗難や紛失、改ざんされる心配がなく、さらに遺言執行時に検認も不要となるため安心して遺言書を残すことができます。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリット・デメリットとしては以下のようなものがあります。
公正証書遺言のメリット
- 様式不備により無効となる心配がない
- 紛失や盗難、改ざんの心配がない
- 遺言執行時に検認が不要
公正証書遺言のデメリット
- 手数料や専門家に依頼する費用がかかる
- 公証人との打ち合わせややりとりが必要
- 立ち会ってもらう証人が必要
- 遺言の内容が証人や公証人に知られる
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言と公正証書遺言を比較すると以下のようになります。

その他の遺言方式
自筆証書遺言と公正証書遺言の他にも遺言には種類があります。
遺言の内容を秘密にした状態で、遺言の存在だけを公証人に保証してもらう秘密証書遺言や、病気で死亡の危険が迫っている場合や船舶・飛行機に乗っている時の非常時に遺言を残す特別方式遺言などいくつかありますが、一般的にあまり使われることがないので、ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言に絞ってご紹介しました。
さいごに
自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違いをご紹介しました。
費用と手間はかかりますが、確実に希望を伝えることができる公正証書遺言の作成をおすすめします。
遺言書作成については当事務所でもご相談に応じておりますのでお気軽にご相談ください。