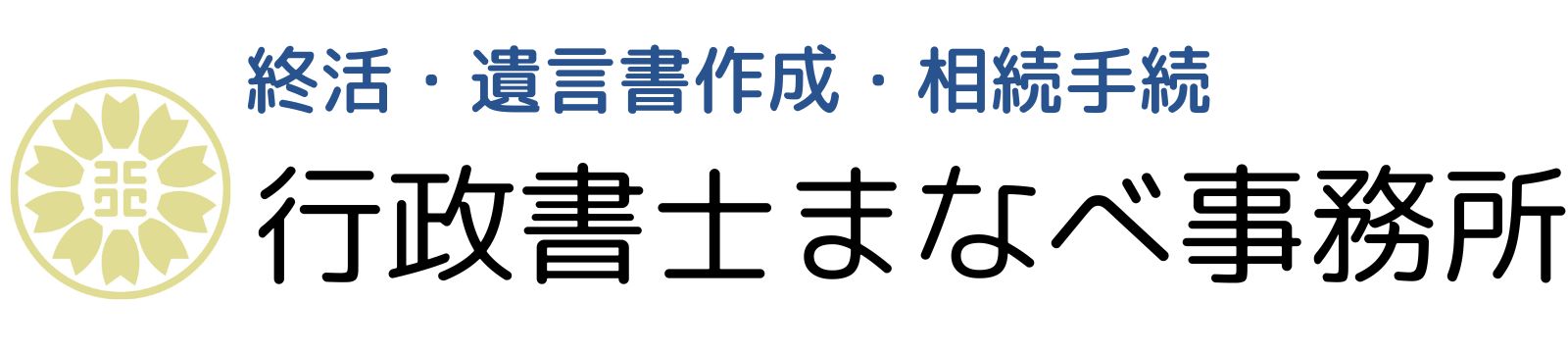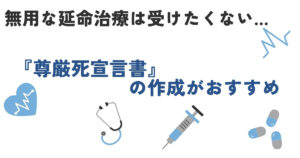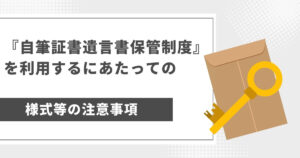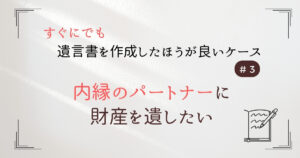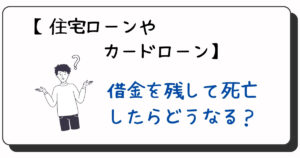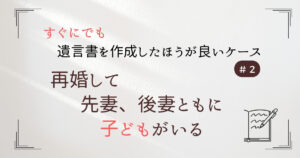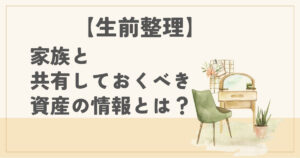『公正証書遺言』の作成手順 一般的な流れと作成後の留意点
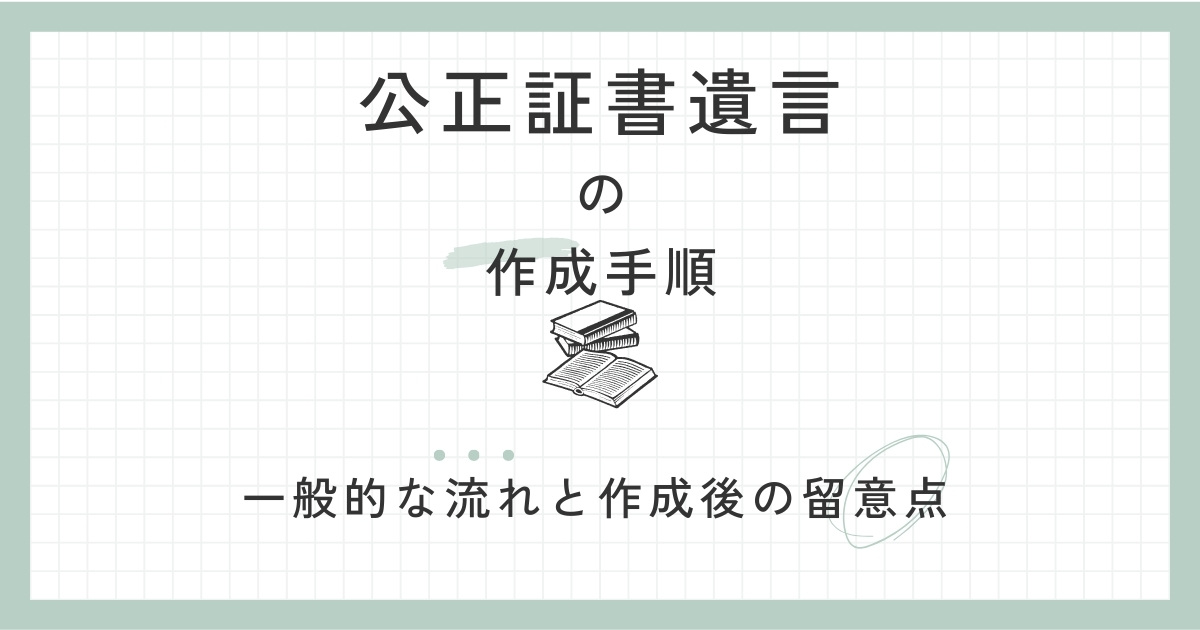
ここでは、一般的な公正証書遺言の作成手順、作成当日の流れ、また、作成後の留意点をご紹介します。
公正証書遺言の作成手順(事前準備)
1. 必要書類を用意する
公正証書遺言を作成するにあたり、必要な書類は以下のようなものがあります。
印鑑登録証明書
公正証書遺言には実印を押印しますので、印鑑登録証明書が必要です。
印鑑登録証明書は公正証書遺言作成時に発行後3か月以内のものが必要です。
もし実印を作っていなかったり、印鑑登録が済んでいない場合は早めに作成・登録をするようにしてください。
遺言作成者の補助証明書
補助証明書とは運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認をするために必要になります。
戸籍謄本
遺言者である遺言書作成者と相続させる相続人との続柄がわかる戸籍謄本が必要です。
(遺贈をする場合)受遺者の住民票など
遺言者の財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票などが必要になります。(その受遺者の住所がわかる手紙やハガキでもよい場合があります。)
直近の固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
財産の中に不動産がある場合必要になります。
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
公正証書遺言の中で、不動産の所在・地番等を特定する事項を記載するために必要です。
ただし、遺言書の中で個々の不動産の特定をしない場合は、不要です。
金融資産の資料(通帳またはそのコピー等)
預貯金等の預貯金口座を特定するために必要になります。
メインバンクの通帳または見開きページ(通帳を開いたページ)の写しなどを用意してください。
なお、この資料は遺言書に記載する金融資産に関するもののみでかまいません。
その他、貸金庫の情報や有価証券がある場合は証券会社の情報も併せて用意します。
証人の確認資料
公正証書遺言を作成する場合、作成の場に立ち会う証人が2名必要です。
遺言者自身で証人を手配する場合は、証人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」などがわかる資料を用意してください。
遺言執行者の特定資料
遺言者が遺言執行者を選任する場合には遺言執行者の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」などがわかる資料を用意してください。
相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は不要です。
これらの中でも取得に手間のかかる戸籍謄本、住民票、登記事項証明書は行政書士にて取得することもできますので、お申し付けください。
2. 文案を作成する
遺言書に残したい内容を収集した情報をもとに文案を作成します。
公正証書遺言は自筆証書遺言と違って、自ら記入が必要なのは氏名だけです。
そのため、専門家に作成を依頼した場合、お話をうかがって文案を作成しますので、最終的にはできあがった文案の内容を確認して署名・押印をするだけなので、文字数を気にせず作成することができます。
3. 公証人と打合せをする
文案を作成したら、公正証書遺言を作成したい公証役場に予約を入れて公証人と打合せを行います。
「相続関係説明図」と「作成した文案」および用意した必要書類を提出し、以下の事項を報告したうえで、文案について検討が行われます。
- 遺言を残すに至った経緯・動機
- 証人の候補の有無
- 希望する作成日時等のスケジュール 等
なお、公証役場での遺言書作成は全国どこの公証役場でも可能ですが、遺言者の自宅や入院先等に公証人に出張してもらう場合は、出張先の都道府県の公証役場に依頼しなければなりません。
4. 公証人から文案・費用が提示される
打合せから1週間ほどで公証役場から文案と費用の見積が提示されます。
文案が提示されたら、次のポイントを確認してください。
- 遺言書に残したい自分の意思が文案に反映されているか
- 自分の作った文案との相違点
- 遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者、証人の住所・氏名・生年月日
- 土地・建物が登記事項証明書のとおり記載されているか
- 金融機関名・預金の種類・口座番号
- 貸金庫がある銀行名・支店名 等
疑問点や修正がある場合は行政書士または公証人へ問い合わせをしてください。
文案の内容で問題なければ、依頼した行政書士・公証人・証人で予定を調整し、公証役場での遺言書作成の日時を決めていきます。
当日は公証人手数料と印鑑登録証明書、実印、補助証明書を忘れずに持参してください。
※公正証書遺言の作成手数料はこちらをご確認ください。
公正証書遺言の作成手順(作成当日)
ここからは公正証書遺言作成当日に公証役場で行われる一般的な流れをご紹介します。
公証役場において公証人を前に遺言作成者、証人2名とともに出席します。
これは遺言者の本人確認をするためです。
同じくこちらは証人の本人確認が行われます。
遺言者に遺言能力があるのか、また自分の意思で遺言を残すかを公証人が確認します。
事前に公証人と打合せをした文案を公証人が読み聞かせ、内容に間違いがないか確認をします。
遺言者は「実印」を押印し、証人は「認印」または「職印」でも可能です。
以上で公正証書遺言は完成です。
その際、公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付されます。
正本と謄本の法的効果に違いはありません。
原本は公証役場に保管され、実務上は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとなっています。
最後に公証役場に「手数料」を現金で支払って完了です。
公正証書遺言作成後の留意点とは
公正証書遺言を作成したからといってこれで自分の死後すべて順調に進むかといったらそうとは限りません。
実際、遺言者が死亡した時点で遺言書を預けてある公証役場が遺言執行者に対して公正証書遺言を作成した事実を通知してくれるということは現時点では行われておりません。
つまり、公正証書遺言を残していたとしても、その存在が遺言執行者や相続人に知られずに、遺言が執行されない恐れもあります。
したがって、公正証書遺言を作成した場合は、遺言者以外の者(遺言執行者や相続人)に遺言書の保管を託さなければなりません。
この場合、遺言書の保管者は遺言者であるあなたの死亡を直ちに知ることができる立場の者でなければなりません。
一般的には、遺言執行者が「正本」を、遺言者が「謄本」を保管することが多いようです。
なお、遺言書は銀行の貸金庫に預けるのは避けた方がよいでしょう。
貸金庫を開ける際に、銀行から相続人全員の署名押印を求められるおそれがあり、すみやかに遺言書を確認することができなくなるためです。
遺言書はいつでも撤回できる
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
遺言を撤回したいときは、公正証書遺言の作成を依頼した専門家、または公証役場へ連絡をしてください。
さいごに
以上が公正証書遺言の一般的な作成手順の流れです。
ご自身ですべてやろうとすると、用意する書類も多く、公証人との打合せなど、手間と時間がかかります。
公正証書遺言の作成を行政書士など専門家へ依頼することで、大部分を代わりに行ってもらうことができるうえ、的確なアドバイスを得ることも期待でき、比較的短時間で遺言書を完成させることができるというメリットもあります。