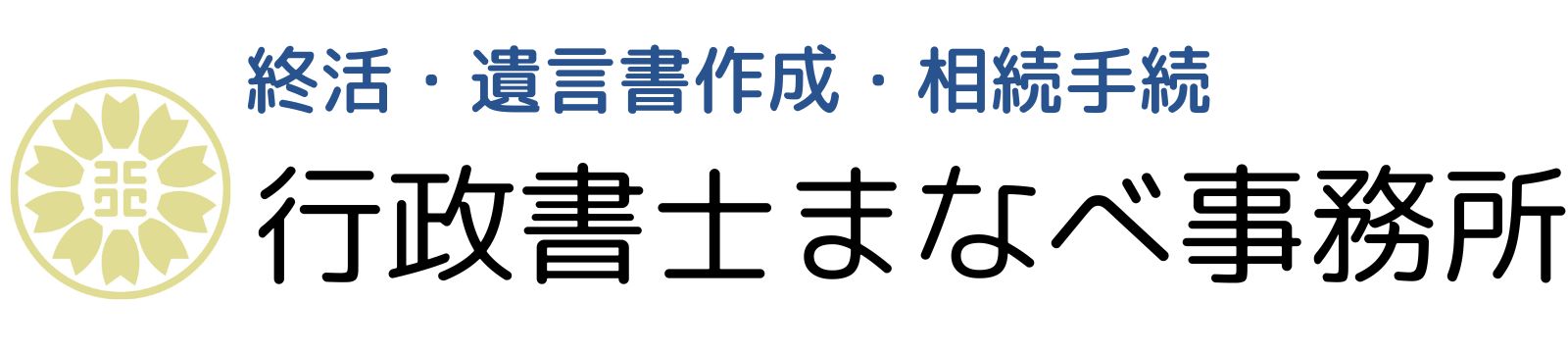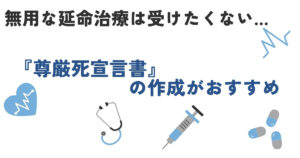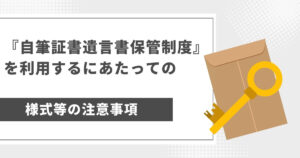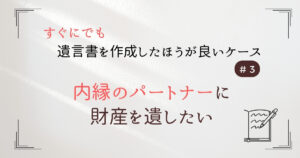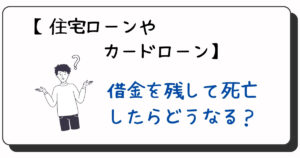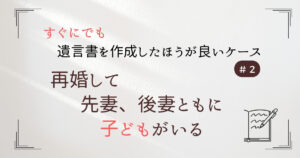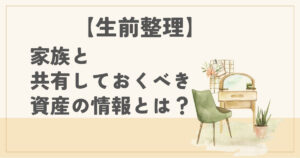遺言書を作成する前に考えておきたい大切なこと
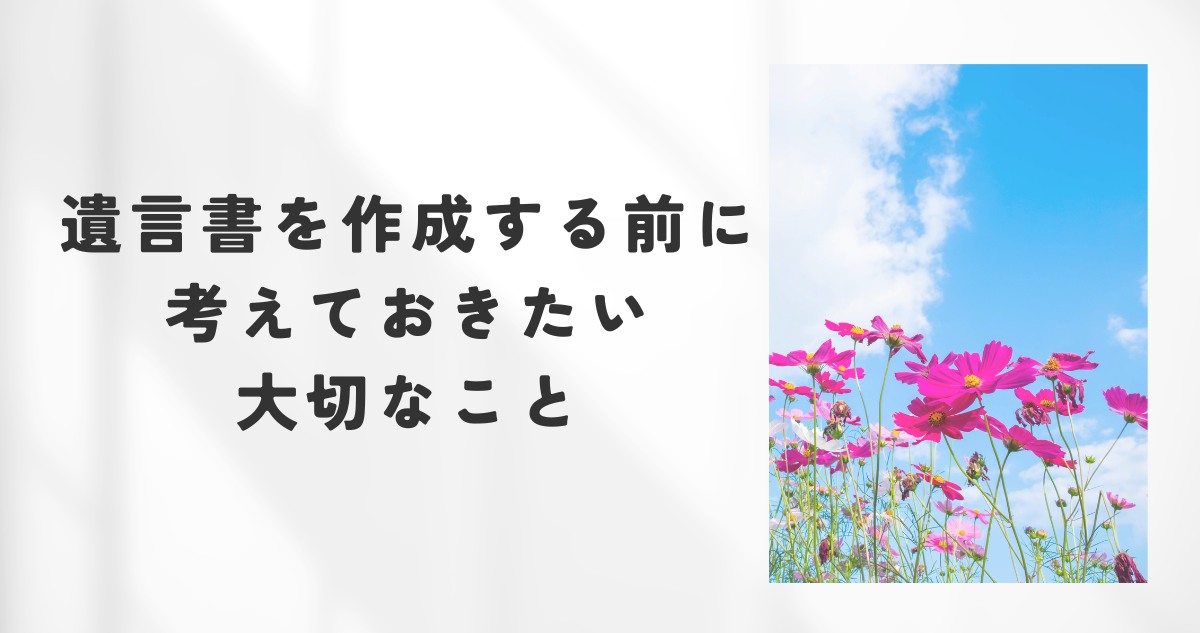
遺言書を作成するなかで、この財産は誰に相続させよう、こっちの財産はどうしようかと迷うこともでてくるでしょう。
遺言書を作成するにはまず、なぜ遺言書を残そうと思ったのか、残された家族にどのように生活して欲しいのか、心配事はなにかなどを考えて明確にすることが大切です。
そうすることで、遺言書を作成しているなかで迷いが生じた時にも解決の糸口が見つかります。
遺言書を作成するにあたって考えておくこと
残された家族の生活が守られるようにする
今現在、あなたのご家族があなたの収入で生活している場合、あなたの死後、その人たちの生活が困らないような方法で遺産を分けることを考えなければなりません。
具体的には配偶者の住む場所を確保し、生活をしていけるだけの現金も残してあげるようにする必要があります。
具体的には配偶者居住権を取得させるように遺言書に記しておくなど、残された配偶者や家族の生活が守られるようにするとよいでしょう。
揉めやすいのは不動産
遺産相続、遺産分割協議において不動産はなにかと揉め事が起こりやすいといえます。
その理由としては、
- 不動産は管理が大変
- 売却にも手間がかかり、分けるのも大変
といったことが挙げられます。
分けづらいからと不動産を共有にすると売却などをする場合、意見が対立し、その不動産を共有している相続人同士のトラブルに発展するケースもあります。
そのため、不動産はなるべく共有しないほうがよいでしょう。
トラブルの元にならないように不要な不動産は早めに処分したり、相続させる相手を早めに決めるなど、不動産を柱に遺産の分配を考えるのもおすすめです。
相続税について確認しておく
相続を受けると相続税という税金を支払う必要があります。
ただ、この相続税は相続を受けたすべての人が支払う必要がある税金ではありません。
相続財産(遺産総額)が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりませんが、それを超えてしまうと相続税を納める必要があるのです。
例えば夫が亡くなって、妻と子ども2人が残された場合は、法定相続人は3人となるので、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3)」で、4,800万円となります。
つまり、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず、税務署に申告をする必要もありません。
場合によっては多額の税金を納めなければならないケースもあります。
現金で相続をすれば、その中から相続税を納めればよいのですが、必ずしも現金で相続するとは限りません。
その場合に備えて、相続財産を処分したり、相続財産以外から納める税金を工面しなくてはいけない場合もあります。
残された家族が相続税で困らないように、ご自身の相続財産が把握できたら相続税がどのくらいになるのかをあらかじめシミュレーションしておくとよいでしょう。
各相続人に不公平感を抱かせないように
遺言書を執行するに際して、各相続人に不公平感を抱かせないようにすることはとても大切です。
例えば、特定の相続人に多めに相続をさせたいという事情がある場合、他の相続人に不公平感を抱かせないようにする必要があります。
その場合、他の相続人にも遺留分にあたる額は最低限確保したり、その遺言を残す意図を「付言事項」に記すようにするなど相続人の理解を得るように努め、相続人間に争いが起きないように配慮することが必要です。
さいごに
遺言書を作成する前に考えておきたいことをご紹介しました。
遺言書を作成するとなると、どうしても相続人の思惑がぶつかり合うことも出てきてしまいます。
遺産相続の現場においてはどうしても強い立場の人が自分に有利に都合のよいように遺産を分けようとすることが多いのが現実です。
立場の弱い人が自分のことを主張できずにつらい思いをしないように、親が遺産分けの方針を遺言書で示すことはとても大切なことです。
将来その遺言書を見て文句を言う人がいるかもしれませんが、何もせずに子どもたちに任せっきりで争いが生じてしまうくらいなら憎まれ役を進んで買って出てください。
そのためにはここでご紹介したポイントを参考にしていただき、日頃から相続人としっかりコミュニケーションを取っていただきたいと思います。