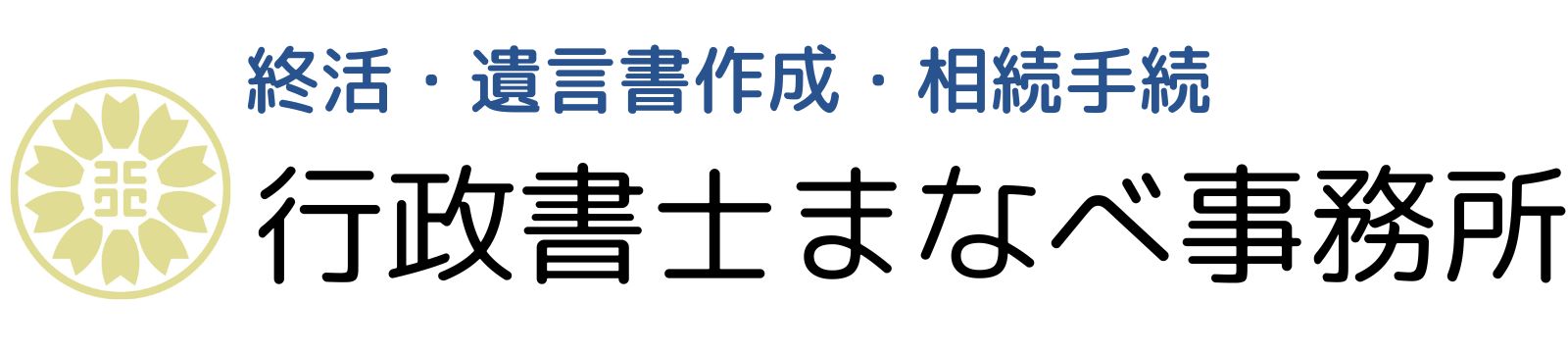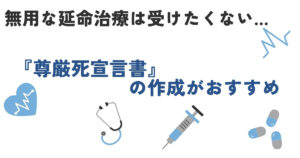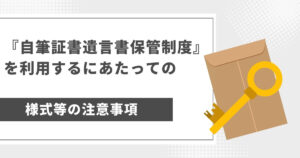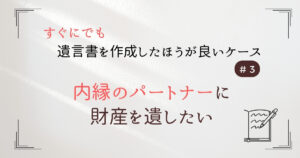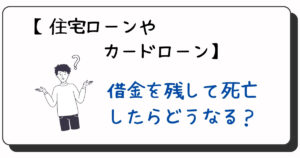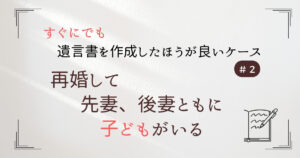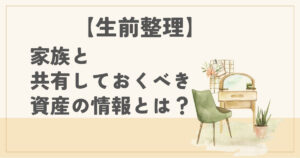子どもたちは仲が良いけれどそれでも遺言書は必要?
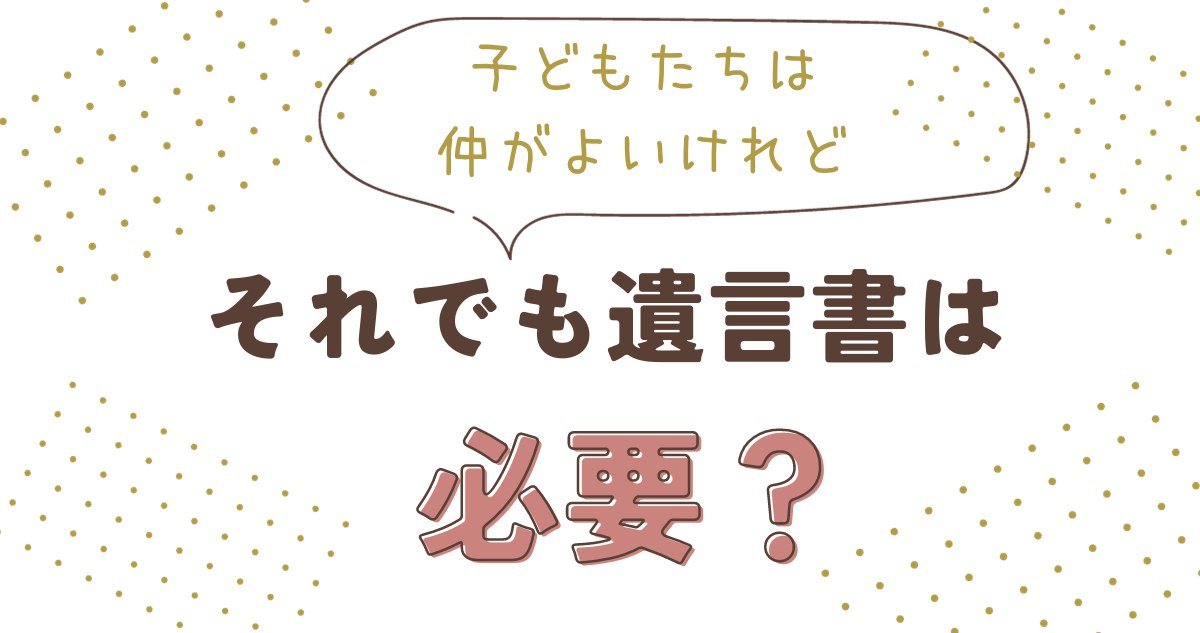
「遺言書を書くほどうちには財産がない」、「うちは子どもたちの仲が良いから仲良く平等に遺産を分けてくれるだろう」。
多くの方がこのように考えているのではないでしょうか。
しかし、財産が少なくても、兄弟姉妹の仲が良くても油断はできないのです。
二次相続は特に相続争いが起こりやすい状況
両親ともに健在の場合に、いずれか一方が亡くなった場合の相続を「一次相続」といい、その後に残されたもう片方の親が亡くなった場合の相続を「二次相続」といいます。
この一次相続の場合、家族の仲がよければ争いに発展することはあまり多くありません。
たとえ子どもたちが不満を抱いていても、生存している親が間をとりもって抑えることができるからです。
しかし、二次相続ともなると話は変わります。
すでに両親がおらず、残されるのは子どもたちだけになりますから、だれかが不満を抱くとそのまま争いに発展することになってしまいます。
その子どもたちにとっては親から相続できる最後のチャンスにもなるのでなおさらです。
また、たとえ兄弟姉妹の仲が良くても、その配偶者や親戚が相続に不満を持ち、口を出してくるということも十分にありえます。
たとえ財産が少なくてもその少ない財産の中からいかに多く確保しようかという考えも働きます。
そのため二次相続では争いが起こる可能性が一次相続よりも高くなるのです。
法定相続分どおり分けるような遺言は無意味か?
兄弟二人で法定相続分どおり半々で遺産を分けてほしいと考えている場合、法定相続分どおりなのだから遺言書を書く必要はないのでしょうか?
これについてはそうとも言い切れません。
なぜなら、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこない、財産の帰属を決めることになります。
通常であれば、法定相続分に応じて平等に分けるところ、遺産分割協議を行えば法定相続分を無視した分け方をすることも可能なのです。
つまり、兄に反論できない弟がうまく兄に言いくるめられて法定相続分よりも少ない割合で合意させられるということも起こり得るのです。
遺産分割協議の場は特に欲望が絡む場所でもあるので、発言力のある人が自分に有利に進めようとすることも想像できます。
したがって、たとえ法定相続分どおりに分けてほしいと思っていても、兄と弟に法定相続分どおりに2分の1ずつ相続させる内容の遺言書を残す意味は十分にあります。
遺言書を書いたからといって安心はできない
遺言書を残したとしても、相続人全員が同意すれば、遺言書とは違った内容の遺産分けをすることもできてしまいます。
そのため、自分の意見を主張できずに少ない財産しか相続できないといった事態が発生するかもしれません。
そのような心配のある子どもがいる場合は、その子どもを遺言執行者に指定するなど特に配慮してあげるとよいでしょう。
そうすることで、相続発生後すみやかに遺言を執行できるようになります。
遺言者は、遺言者の有するすべての預貯金を、長男〇〇(平成〇年〇月〇日生)及び二男〇〇(平成〇年〇月〇日生)に2分の1ずつ相続させる。遺言執行者として、二男の〇〇を指定する。
財産に不動産などがある場合は注意が必要
財産が預貯金だけであれば簡単に半分ずつ分けることができますが、不動産など分割しにくい財産がある場合は注意が必要です。
その場合、遺言書に「全財産を2分の1ずつ相続させる」と書くのはおすすめできません。
不動産を複数の相続人で平等に分けて共有すると、将来、売却や賃貸などをする場合に他の相続人の同意を得るなどの手続きが必要になり、うまく進まないという例もあるからです。
その場合は、不動産は長男、預貯金は二男になど個別の財産ごとに相続させるか、その不動産を売却し、売却代金から費用などを差し引いた残りの金額を2分の1ずつ相続させるなどの方法もあります。
遺言書にはなるべく個別の財産ごとに相続させる旨を記載したほうが安心です。
遺言者は、遺言者の所有するすべての財産を換価し、その換価金から諸費用を控除した残金を長男〇〇(平成〇年〇月〇日生)及び二男〇〇(平成〇年〇月〇日生)に2分の1ずつ相続させる。
さいごに
兄弟姉妹の仲が良くても、両親が亡くなってしまうと子どもたちの抑えがきかなくなり、争いに発展することがあります。
あなたの亡き後、将来家族が仲良く暮らしてほしいと願うのならば、争いの起きないような遺言書を残すのが親としてできる最後のつとめだと考えます。
将来に不安のある方はお気軽にご相談いただけたらと思います。